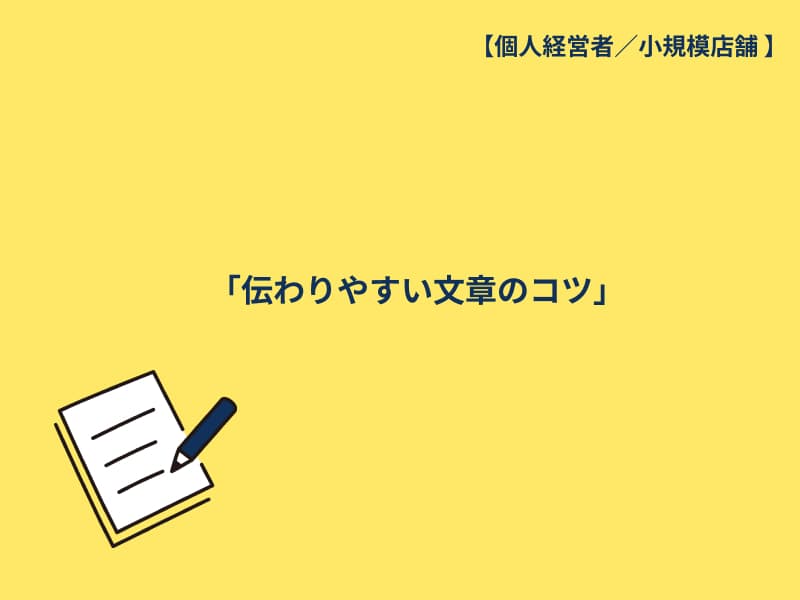
目次
はじめに
ホームページやSNSなど、Web運用における「文章の書き方のコツ」を整理した記事です。
こんな方にむけて書きました
- 個人経営者 で、今よりも伝わりやすい文章を書けるようになりたい
- 文章はSNSなどで書くことがあるが、苦手意識がある
わたしはライターや編集の専門家ではありません。
ただ広告関係の仕事で、お客さまが伝えたいことを代わりに書いたり、お客さまが用意した文章をより伝わりやすく編集したりする業務を20年以上やってきました。
今は、個人経営者やスタッフ自身がスマートフォン1つで文章を気軽に発信できる時代です。
事業のことを誰よりも考え、誰よりも詳しい個人経営者が文章を書くのに、今ほど理想的な環境はかつてなかったでしょう。
でも実際にわたしの仕事だと、個人経営者・スタッフが「文章の伝えやすい書き方は学校で習ってもいないし、業務によっては一度もきちんと習ったことがない」・・・という人が多いのです。
そこで仕事でお客さまによくお伝えしている内容を中心に、有名な先生が書いた文章本なども引用しつつ、伝わりやすい文章のコツを整理しました。
「伝わりやすい文章」はどんな文章?
もっとも読んでほしい人が、読みやすくて理解しやすい文章です。
そのための原則です。
- 「最も読んでほしい人」を考える
- 「最も読んでほしい人」が読みやすいか
- 「最も読んでほしい人」が理解しやすいか
「わかりやすい文書」のために意識するとよいと思う原則3つ
- 1文を短く 100文字以内
- 中学生もおかんも理解できる
- ひらがなと漢字のバランス 7:3ぐらい
1.文を短く 100文字以内
長い話はダメです。
絶対ルールはありませんが、目安として100文字を超えたら長いかも?もっと短くできる?と疑ってOKです。
会話だと続けて話しちゃいがちですが、文章ならたいてい「です」「ます」で区切りをつけることができます。
会話と同じように、文章も原則としては短いほうが伝わりやすいのが鉄則です。
2.中学生とおかんでもわかる文章に
これは「最も読んでほしい人」にかかるところです。
意図的な場合を除いて、中学生でもわかるのがいいですね。
自分でもあいまいだったところを調べて書かないとできません。
内容をちゃんと理解していないと書けないのです。
運営中の観光Webメディアでは、自分の母でもわかる文章にしています。
おかんがわかるってことは、その観光地を知らない人にもある程度伝わるということになるからです。
3.ひらがなと漢字のバランス 7:3ぐらい
漢字がいっぱいだと、硬くて読む気が起きません。
中国語っぽくなるし。逆にひらがなばっかりだと、幼稚な文章になってしまいます。
例えば「させて頂きます」「…して下さい」とかおまけ的な補助動詞(動詞にくっついて、それ自体は意味うすい)はひらがなにするだけで読みやすく伝わりやすくなります。
「させていただきます」「してください」などですね。
このブログだと、ひらがなと漢字の比率は8対2ぐらいでしょうか。
「わかりやすい文書」のためのコツ その他
- 結論から
- 修飾語は長いものを先にする
- !はマジでびっくりなときに限定する
- リズムを大切に
- 意味が含まれる率を高める
- 外来語よりも日本語
結論から
定番ですね。
芸能人とか影響力が大きい人でない限り、ほとんどの場合で全文は読まれないという前提を知っておいたほうがいい。
スマートフォンで、何かをしながら、スッスッと流しみ読みされます。
だから結論からいわないとだめ。
そしてなんの事かわからないとだめです。
修飾語は長いものを先にする
大原則。
修飾語がいくつか重なる場合、長いをほう先に書くほうが読みやすくなります。
リズムを大切に
語尾が揃いすぎないよう変化をもたせるとリズムをもたせます。
ためしに「です」か「ました」を3連チャンな文章を作ってみてください。
うざくなることがわかります。
外来語よりも日本語がわかりやすい
ジャパンです。
熟語を含む音読みは、会話ではわかりづらいです。
文章だと少しましになりますが、やっぱり日本語が1番。
しゃべり口調の文章がわかりやすいのも、日本語が多くなるからなはず。
- 施錠をする→「カギをかける」ってふつーに言ってください
- 長寿→「長生き」ってふつーに言ってください
意味が含まれる率を高める
ムダをなくすってことです。
デキる人は、少ない文章の中に意味がたくさんあります。
逆のメールは、長いわりに意味がスカスカです。
とくに仕事の場合では、必要ですね。
ブログは仕事でない場合もありますが、意味のない言葉を除くだけでもいいです。
!はマジでびっくりなときに限定する
やたらと!が多い文章、よく見かけませんか?
おはようございます!昨日は超話題のラーメン屋に行きました!とてもおいしかったです!また行きたいと思います!それでは!
…ぜんぶ大事かよ!
結局何を強調したいのかわからなくなってしまいます。
「伝わりやすい文書」を書く練習方法
書くことです。
本気なら毎日書くこと。
インターネットの普及で、ちゃんと書くことはほぼ誰にでも必要な時代です。
プロのライターや編集の人でなくても、必要です。
プロじゃなくても上手に書きたくなりたいなら、書くことです。
書くことの練習は、今だとやっぱりブログが最も手軽ですね。
書くということは考えることなので、考える練習にもなります。
野口 悠紀雄さんの「超」文章法で読んで印象に残っているのが、あるテーマについて詳しくなりたかったら、本を書けやというアドバイスです。
矛盾しているようで、そのとおりなんですね。
本を書くこということは、めっちゃ調べてめっちゃ考えるので、そのテーマに詳しくなるに決まっているのですね。
実際には本を書くまでできなくても、ブログを書くことならハードルはぐっと下がります。
わたしも観光サイトを運営することで、5年間で記事を400以上書きました。
結果「このエリアのことはコイツに聞けばOK」的存在になりました。
超いなかエリアでありますが、それなりに詳しくなったと思います。
世の中の物事について、ちゃんと書いた人が多いほど、考えた数が多くなり、考えが深くなります。
わたしのまわりを見渡しても、文章が上手な人はほぼ、自分の考えをしっかりしている人です。
「伝わりやすい文書」参考本
文章に関するいろんな本を読みまして、とくに影響を受けた本を書いておきます。
ステップ① 文章を書くのが苦手だけど、少しでも前へ進みたい人向け(励ましの本)
読むだけで「書く力」が劇的に伸びる本―作文指導のプロが教える大人のための文章講座
わたしにとって、「文章を書くことの抵抗」がなくなるきっかけとなった思い出の本。
作文の本です。
わたしは学生の頃までは文章を書くことがほんとうに苦手でした。
文章をうまく書きたいとは思っていましたが、国語の成績は最低レベルで本もほぼ読まない人だったので、ずっと苦手意識がありました。
そのためちょっとでも長い文章を書くことが苦痛でした。
でもこの本を読むことで「自由に書いていいだ」という気持ちになり励まれた本です。
個人的に殿堂入り間違いなしなほどためになったのですが、著者は最近本を出されていないようです。
2023年に買い直して読み直しまして、やっぱりオススメできる本です。
ステップ② 文章を書くの苦手ではなく、上達したい方
【新版】日本語の作文技術 (朝日文庫)
文章を書くルールの基本。
文章について、学校では最初は1マス空けてとか、あまり意味があることを学べませんでした。
でもこの本を読んで伝わりやすい文章にはちゃんとルールがあることを知りました。
説明不要の超有名本で、文章ルール系で最も影響を受けたかも。
またこの本に影響を受けた文章本も無限にありますので、今はもっとわかりやすい本があるかもですが・・・原点です。
キンドル版もでたようです。
「ひらがな」で話す技術
いろんな文章本がある中で、この切り口ははじめてでないだろうか?
タイトルのとおり「ひらがなで話すこと」を勧める本でして、いまも他に読んだことがありません。
「ひらがなで話すこと」は、そのまま「伝わりやすい文章を書く」ことにつながります。
個人的に世界を変えてくれた1冊です。
「超」文章法 (中公新書)
テーマは1つしましょうと、先生は言っています。
オンライン無料情報提供】訪問数が2年で5倍になった飲食店の事例をお話します(毎月2店舗 限定)
飲食店経営者さま限定企画です。1回30分。
栃木県にある飲食店です。
「Googleマップ 検索順位 カテゴリー1位」「Google検索順位 カテゴリー1位」「LINE 10月で友達2,000人超え(月1投稿のみ、広告なし)」「来店者平均年齢 5歳若返り」「予約業務効率化」
・・・など、具体的な事例をお話しします。
飲食店のWeb運用をする上で参考になるヒントが得られるかと思います。
<申込方法>
以下、公式LINEをクリックして(今年度からはじめました)メッセージをお願いします。
確認できしだい、日程の候補をご返信します。